『ビラヴド』トニ・モリスン その5
昨日、Netflixで途中にしていた映画『この世界の片隅に』を最後まで鑑賞しました。
どこにでもいるような、ごくふつうのわたしたちが、あの戦時下を生きるというのはどういうことか。
そういう物語であるように感じました。
誰にも咎められていないけど、現代アメリカに持ち込んで見るのは気が引けるような思いがするくらい、主人公が戦時下に置かれてしまったごくふつうのわたしたち、なのでありました。
さて、ここからは、学校の課題で書いた英語エッセイを振り返りながら、ああだこうだ言ってみる企画の続編です。
ノーベル文学賞受賞作家であるトニ・モリスンの代表作『ビラヴド』にまつわるエッセイを取り上げています。
この企画の、ひとつ目の記事はこちら。
After treating sick-state Beloved in Denver’s own room, the sisters began to spend a sweet secret time together. However, one day in an unexpected turn of events, Beloved made it clear that she came back there not for Denver but for Sethe. As Sethe came to realize that Beloved was the returned child of hers, she decided to give this once-missing child everything she could. Although Beloved escalated the level of her demands, Sethe stuck to her original resolve. Due to her excessive devotion to Beloved, Sethe got fired from her long-serving restaurant work and wasted the $38 of life savings on “ribbon and dress goods” (Morrison, 282) just aimed at pleasing Beloved. According to Denver’s interpretation, “Sethe was trying to make up for the handsaw; Beloved was making her pay for it” (Morrison, 295). When there is such a strong in-house logic exists apart from and disputing with the social logic, the society deems that company illogical, abnormal, and insane. As the tie between Sethe and Beloved gets strengthened, the readers find some sort of insanity taking over 124, and Sethe.
昨日から引き続き、デンバーちゃん視点でザッと物語の筋を追っていくという作業を行っているパートです。
筋の再生、読みの再確認、前提事項の共有。
こういうところは技術がいるし、エッセイの大部分を占めるもので、構成としてもとても大事です。
しかし、熱量が自動的にほとばしってくれるようなパートではないので、淡々と進めて行くことが重要です。
After treating sick-state Beloved in Denver’s own room, the sisters began to spend a sweet secret time together. However, one day in an unexpected turn of events, Beloved made it clear that she came back there not for Denver but for Sethe.
まず序盤の部分。
マイシスターの面倒はわいが見ちゃるぞ! と意気込んだデンバーちゃんでしたが、振られてしまいます。
「悪いけど、あんたのために戻ってきたわけじゃないから。
セサのためなの。邪魔しないでくれない?」
とビラヴド。
さんざん尽くしてきたのに、邪魔者あつかい。
デンバーちゃん、かわいそうです。
As Sethe came to realize that Beloved was the returned child of hers, she decided to give this once-missing child everything she could. Although Beloved escalated the level of her demands, Sethe stuck to her original resolve. Due to her excessive devotion to Beloved, Sethe got fired from her long-serving restaurant work and wasted the $38 of life savings on “ribbon and dress goods” (Morrison, 282) just aimed at pleasing Beloved.
続いて、中盤。
セサがビラヴドの正体に気づいたところで、心のタガが外れてしまいます。
心の奥の奥に仕舞い込んでいたのですよね。
その、一生使わないはずの感情は。
ところが、起きるはずのないことが起きたことで、その愛を傾けることができるようになった。
あの見果てぬ生を生きることが可能になった。
セサは、その幸せのためだけに、彼女の持ちうるライフを蕩尽していきます。
According to Denver’s interpretation, “Sethe was trying to make up for the handsaw; Beloved was making her pay for it” (Morrison, 295). When there is such a strong in-house logic exists apart from and disputing with the social logic, the society deems that company illogical, abnormal, and insane. As the tie between Sethe and Beloved gets strengthened, the readers find some sort of insanity taking over 124, and Sethe.
この段落最後の部分です。
セサはそうすることによって罪滅ぼしをしていました。
ビラヴドは、セサに罪滅ぼしをさせていました。
デンバーちゃんはふたりをそう見ていました。
ふたりは通常の社会からかけ離れたロジックで行動していきます。
外側にいるぼくらはそれを狂気と見做すのです。
というところ。
「the handsaw」というのは、セサが子殺しのために使った凶器のことです。
逃亡奴隷の身であったセサは、ある日、4人の男たちが奴隷である自分とその子供たちを捕まえるために近づいてくるのを見て、発狂します。
プランテーションに連れ戻されて、奴隷生活を強いられるくらいなら、死んだほうがマシだ。
特に子どもたちには、あんな思いをさせたくない。
あんな目に合わさせるくらいなら殺してしまったほうがまだいい、と電撃的に直感し、手近にあった「handsaw」でもって、当時いちばん小さかった赤子=ビラヴドを殺してしまいました(そのときはまだデンバーちゃんは生まれていません)。
これ、最初のエントリーでも書きましたが、この物語のコアとなる部分のひとつです。
一番のコアは、奴隷と、子殺しと、黄泉帰りであると。
ところが、わたくしのエッセイでは、デンバーちゃん視点からの再編集というところにこだわりすぎてしまい、結局その部分の記述を盛り込みませんでした。
これはいくらなんでも、失敗だったなーと思っているところです。
たとえ、読者全員が本を読んでいるという前提であっても、ここのところを外すのはよくなかったですね。
そのために、ここの「the handsaw」が唐突になりすぎてしまいました。
はんせー。
(つづく)

- 作者: トニモリスン,Toni Morrison,吉田廸子
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 1998/12
- メディア: 文庫
- 購入: 3人 クリック: 23回
- この商品を含むブログ (12件) を見る
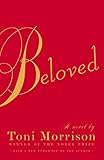
Beloved (Vintage International)
- 作者: Toni Morrison
- 出版社/メーカー: Vintage
- 発売日: 2004/06/08
- メディア: ペーパーバック
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (4件) を見る

