『ビラヴド』トニ・モリスン その6
掃除のおばさんが家を掃除してくれている間、家にいるときはベランダに避難するのですが、ベランダにいるとときどき、ハチドリの訪問を受けます。
かわいいサイズ感ですが、あいつらなかなかに図太い精神をもっていて、結構な距離まで接近してきます。
つかまえまえちゃろか!?
といって、手を伸ばすと、簡単に逃げられてしまいます。
そんなつもりもないくせに、と鼻で笑われている気がして、あまりいい気分ではありません。
さて、ここからは、学校の課題で書いた英語エッセイを振り返りながら、ああだこうだ言ってみる企画の続編です。
ノーベル文学賞受賞作家であるトニ・モリスンの代表作『ビラヴド』にまつわるエッセイを取り上げています。
この企画の、ひとつ目の記事はこちら。
In an earlier chapter, Paul D had warned the readers as “Risky, thought Paul D, very risky. For a used-to-be-slave woman to love anything that much was dangerous, especially if it was her children she had settled on to love” (Morrison, 54). Also, in Denver’s monologue, she implied Sethe’s insanity by stating that “I love my mother but I know she killed one of her own daughters, and tender as she is with me, I’m scared of her because of it,” and that “I’m afraid the thing that happened that made it all right for my mother to kill my sister could happen again” (Morrison, 242). Out of such fear, Denver had a recurring nightmare of being tenderly cut her head off by her mother, and also, longed for the protection from her daddy, whom she had never seen before. Morrison described the developing status of 124 as “The bigger Beloved got, the smaller Sethe became” (294). However, it could also be described as ‘the weaker Sethe got, the stronger Denver became.’ In fact, the third and final part of Beloved is almost fully dedicated to heroic Denver’s growing-up story.
というこの部分です。
元のエッセイは、ワードで6ページほどあるのですが(12pt・行間ダブルスペース)、今回の分で4ページ目の後半までカバーできるという感じです。
この進み具合だと、あと3回くらいの更新で完走できそうです。
さて、前回のエントリーでは、子殺しの罪を背負うセサが、ビラヴドへ愛を傾けすぎた結果、一般常識から外れてしまい、クレイジーなふるまいを見せるようになったというところまでカバーしました。
今回はその、「セサの狂気」というのをあれこれ検証してみようというのがテーマになります。
In an earlier chapter, Paul D had warned the readers as “Risky, thought Paul D, very risky. For a used-to-be-slave woman to love anything that much was dangerous, especially if it was her children she had settled on to love” (Morrison, 54).
まずは、ポールDさんのコメントから。
「奴隷あがりの女があんなにも何かを愛するというのは、危険だ。
その愛する対象ってのが子どもである場合はなおさらだ」
このコメントは、デンバーちゃんへの愛情の注ぎ方を見た際に発せられたものでしたが、物語後半、セサがいよいよクレイジーになってきたところで、もう一度響いてくるように感じました。
いい布石になっていたなーと。
Also, in Denver’s monologue, she implied Sethe’s insanity by stating that “I love my mother but I know she killed one of her own daughters, and tender as she is with me, I’m scared of her because of it,” and that “I’m afraid the thing that happened that made it all right for my mother to kill my sister could happen again” (Morrison, 242).
一方こちらは、デンバーちゃんからの証言です。
「お母さんのことは大好き。
でも、お母さんが実の子供を殺したということは忘れられないの。
お母さんはとても優しいんだ。
だけど、その過去のせいで私はお母さんのことが怖いの」
さらに、
「それが何だったかはわからないけど、
あの日、お姉ちゃんを殺すことを正当化した何かが
またお母さんに起こるかもしれないと考えると怖いの」
と彼女が抱えていた母へのアンビバレントな思いが吐露されます。
どんなに仲のいい親子みたいでいたときも、デンバーちゃんは心の奥底に拭えない恐怖を抱えていたんだなぁと思うと、とても複雑な気持ちになります。
Out of such fear, Denver had a recurring nightmare of being tenderly cut her head off by her mother, and also, longed for the protection from her daddy, whom she had never seen before.
そのために、デンバーちゃんは、彼女の母親が優しく優しく彼女の首を切り落とすという悪夢を繰り返し見るのだといいます。
これは、おそろしい!
「その3」のエントリーで、「社会とのつながりの乏しい子供にとっての脅威」ということを書きましたが、彼女の生活は、根底のところがそもそも信頼しきれない不安定な代物で構築されていたのだということが明かされます。
そのため、彼女は、まだ一度も見たことのない父親の帰りを強く待ちわびるのです。
(それだから、ポールDがやってきたときに、心底がっかりしたというわけでした)
Morrison described the developing status of 124 as “The bigger Beloved got, the smaller Sethe became” (294). However, it could also be described as ‘the weaker Sethe got, the stronger Denver became.’ In fact, the third and final part of Beloved is almost fully dedicated to heroic Denver’s growing-up story.
本には、
「ビラヴドが大きくなればなるほど、セサは小さくなっていった」
と書かれていたけれど、
わたしは、
「セサが弱くなるに従い、デンバーちゃんが強くなっていった」
というところに着目したい。
そうなんです。
ここから物語は、デンヴァーの成長物語へと変質していくのです。
(つづく)

- 作者: トニモリスン,Toni Morrison,吉田廸子
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 1998/12
- メディア: 文庫
- 購入: 3人 クリック: 23回
- この商品を含むブログ (12件) を見る
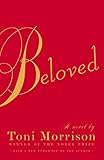
Beloved (Vintage International)
- 作者: Toni Morrison
- 出版社/メーカー: Vintage
- 発売日: 2004/06/08
- メディア: ペーパーバック
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (4件) を見る


