『ビラヴド』トニ・モリスン その6
掃除のおばさんが家を掃除してくれている間、家にいるときはベランダに避難するのですが、ベランダにいるとときどき、ハチドリの訪問を受けます。
かわいいサイズ感ですが、あいつらなかなかに図太い精神をもっていて、結構な距離まで接近してきます。
つかまえまえちゃろか!?
といって、手を伸ばすと、簡単に逃げられてしまいます。
そんなつもりもないくせに、と鼻で笑われている気がして、あまりいい気分ではありません。
さて、ここからは、学校の課題で書いた英語エッセイを振り返りながら、ああだこうだ言ってみる企画の続編です。
ノーベル文学賞受賞作家であるトニ・モリスンの代表作『ビラヴド』にまつわるエッセイを取り上げています。
この企画の、ひとつ目の記事はこちら。
In an earlier chapter, Paul D had warned the readers as “Risky, thought Paul D, very risky. For a used-to-be-slave woman to love anything that much was dangerous, especially if it was her children she had settled on to love” (Morrison, 54). Also, in Denver’s monologue, she implied Sethe’s insanity by stating that “I love my mother but I know she killed one of her own daughters, and tender as she is with me, I’m scared of her because of it,” and that “I’m afraid the thing that happened that made it all right for my mother to kill my sister could happen again” (Morrison, 242). Out of such fear, Denver had a recurring nightmare of being tenderly cut her head off by her mother, and also, longed for the protection from her daddy, whom she had never seen before. Morrison described the developing status of 124 as “The bigger Beloved got, the smaller Sethe became” (294). However, it could also be described as ‘the weaker Sethe got, the stronger Denver became.’ In fact, the third and final part of Beloved is almost fully dedicated to heroic Denver’s growing-up story.
というこの部分です。
元のエッセイは、ワードで6ページほどあるのですが(12pt・行間ダブルスペース)、今回の分で4ページ目の後半までカバーできるという感じです。
この進み具合だと、あと3回くらいの更新で完走できそうです。
さて、前回のエントリーでは、子殺しの罪を背負うセサが、ビラヴドへ愛を傾けすぎた結果、一般常識から外れてしまい、クレイジーなふるまいを見せるようになったというところまでカバーしました。
今回はその、「セサの狂気」というのをあれこれ検証してみようというのがテーマになります。
In an earlier chapter, Paul D had warned the readers as “Risky, thought Paul D, very risky. For a used-to-be-slave woman to love anything that much was dangerous, especially if it was her children she had settled on to love” (Morrison, 54).
まずは、ポールDさんのコメントから。
「奴隷あがりの女があんなにも何かを愛するというのは、危険だ。
その愛する対象ってのが子どもである場合はなおさらだ」
このコメントは、デンバーちゃんへの愛情の注ぎ方を見た際に発せられたものでしたが、物語後半、セサがいよいよクレイジーになってきたところで、もう一度響いてくるように感じました。
いい布石になっていたなーと。
Also, in Denver’s monologue, she implied Sethe’s insanity by stating that “I love my mother but I know she killed one of her own daughters, and tender as she is with me, I’m scared of her because of it,” and that “I’m afraid the thing that happened that made it all right for my mother to kill my sister could happen again” (Morrison, 242).
一方こちらは、デンバーちゃんからの証言です。
「お母さんのことは大好き。
でも、お母さんが実の子供を殺したということは忘れられないの。
お母さんはとても優しいんだ。
だけど、その過去のせいで私はお母さんのことが怖いの」
さらに、
「それが何だったかはわからないけど、
あの日、お姉ちゃんを殺すことを正当化した何かが
またお母さんに起こるかもしれないと考えると怖いの」
と彼女が抱えていた母へのアンビバレントな思いが吐露されます。
どんなに仲のいい親子みたいでいたときも、デンバーちゃんは心の奥底に拭えない恐怖を抱えていたんだなぁと思うと、とても複雑な気持ちになります。
Out of such fear, Denver had a recurring nightmare of being tenderly cut her head off by her mother, and also, longed for the protection from her daddy, whom she had never seen before.
そのために、デンバーちゃんは、彼女の母親が優しく優しく彼女の首を切り落とすという悪夢を繰り返し見るのだといいます。
これは、おそろしい!
「その3」のエントリーで、「社会とのつながりの乏しい子供にとっての脅威」ということを書きましたが、彼女の生活は、根底のところがそもそも信頼しきれない不安定な代物で構築されていたのだということが明かされます。
そのため、彼女は、まだ一度も見たことのない父親の帰りを強く待ちわびるのです。
(それだから、ポールDがやってきたときに、心底がっかりしたというわけでした)
Morrison described the developing status of 124 as “The bigger Beloved got, the smaller Sethe became” (294). However, it could also be described as ‘the weaker Sethe got, the stronger Denver became.’ In fact, the third and final part of Beloved is almost fully dedicated to heroic Denver’s growing-up story.
本には、
「ビラヴドが大きくなればなるほど、セサは小さくなっていった」
と書かれていたけれど、
わたしは、
「セサが弱くなるに従い、デンバーちゃんが強くなっていった」
というところに着目したい。
そうなんです。
ここから物語は、デンヴァーの成長物語へと変質していくのです。
(つづく)

- 作者: トニモリスン,Toni Morrison,吉田廸子
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 1998/12
- メディア: 文庫
- 購入: 3人 クリック: 23回
- この商品を含むブログ (12件) を見る
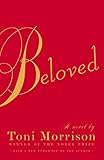
Beloved (Vintage International)
- 作者: Toni Morrison
- 出版社/メーカー: Vintage
- 発売日: 2004/06/08
- メディア: ペーパーバック
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (4件) を見る
『ビラヴド』トニ・モリスン その5
昨日、Netflixで途中にしていた映画『この世界の片隅に』を最後まで鑑賞しました。
どこにでもいるような、ごくふつうのわたしたちが、あの戦時下を生きるというのはどういうことか。
そういう物語であるように感じました。
誰にも咎められていないけど、現代アメリカに持ち込んで見るのは気が引けるような思いがするくらい、主人公が戦時下に置かれてしまったごくふつうのわたしたち、なのでありました。
さて、ここからは、学校の課題で書いた英語エッセイを振り返りながら、ああだこうだ言ってみる企画の続編です。
ノーベル文学賞受賞作家であるトニ・モリスンの代表作『ビラヴド』にまつわるエッセイを取り上げています。
この企画の、ひとつ目の記事はこちら。
After treating sick-state Beloved in Denver’s own room, the sisters began to spend a sweet secret time together. However, one day in an unexpected turn of events, Beloved made it clear that she came back there not for Denver but for Sethe. As Sethe came to realize that Beloved was the returned child of hers, she decided to give this once-missing child everything she could. Although Beloved escalated the level of her demands, Sethe stuck to her original resolve. Due to her excessive devotion to Beloved, Sethe got fired from her long-serving restaurant work and wasted the $38 of life savings on “ribbon and dress goods” (Morrison, 282) just aimed at pleasing Beloved. According to Denver’s interpretation, “Sethe was trying to make up for the handsaw; Beloved was making her pay for it” (Morrison, 295). When there is such a strong in-house logic exists apart from and disputing with the social logic, the society deems that company illogical, abnormal, and insane. As the tie between Sethe and Beloved gets strengthened, the readers find some sort of insanity taking over 124, and Sethe.
昨日から引き続き、デンバーちゃん視点でザッと物語の筋を追っていくという作業を行っているパートです。
筋の再生、読みの再確認、前提事項の共有。
こういうところは技術がいるし、エッセイの大部分を占めるもので、構成としてもとても大事です。
しかし、熱量が自動的にほとばしってくれるようなパートではないので、淡々と進めて行くことが重要です。
After treating sick-state Beloved in Denver’s own room, the sisters began to spend a sweet secret time together. However, one day in an unexpected turn of events, Beloved made it clear that she came back there not for Denver but for Sethe.
まず序盤の部分。
マイシスターの面倒はわいが見ちゃるぞ! と意気込んだデンバーちゃんでしたが、振られてしまいます。
「悪いけど、あんたのために戻ってきたわけじゃないから。
セサのためなの。邪魔しないでくれない?」
とビラヴド。
さんざん尽くしてきたのに、邪魔者あつかい。
デンバーちゃん、かわいそうです。
As Sethe came to realize that Beloved was the returned child of hers, she decided to give this once-missing child everything she could. Although Beloved escalated the level of her demands, Sethe stuck to her original resolve. Due to her excessive devotion to Beloved, Sethe got fired from her long-serving restaurant work and wasted the $38 of life savings on “ribbon and dress goods” (Morrison, 282) just aimed at pleasing Beloved.
続いて、中盤。
セサがビラヴドの正体に気づいたところで、心のタガが外れてしまいます。
心の奥の奥に仕舞い込んでいたのですよね。
その、一生使わないはずの感情は。
ところが、起きるはずのないことが起きたことで、その愛を傾けることができるようになった。
あの見果てぬ生を生きることが可能になった。
セサは、その幸せのためだけに、彼女の持ちうるライフを蕩尽していきます。
According to Denver’s interpretation, “Sethe was trying to make up for the handsaw; Beloved was making her pay for it” (Morrison, 295). When there is such a strong in-house logic exists apart from and disputing with the social logic, the society deems that company illogical, abnormal, and insane. As the tie between Sethe and Beloved gets strengthened, the readers find some sort of insanity taking over 124, and Sethe.
この段落最後の部分です。
セサはそうすることによって罪滅ぼしをしていました。
ビラヴドは、セサに罪滅ぼしをさせていました。
デンバーちゃんはふたりをそう見ていました。
ふたりは通常の社会からかけ離れたロジックで行動していきます。
外側にいるぼくらはそれを狂気と見做すのです。
というところ。
「the handsaw」というのは、セサが子殺しのために使った凶器のことです。
逃亡奴隷の身であったセサは、ある日、4人の男たちが奴隷である自分とその子供たちを捕まえるために近づいてくるのを見て、発狂します。
プランテーションに連れ戻されて、奴隷生活を強いられるくらいなら、死んだほうがマシだ。
特に子どもたちには、あんな思いをさせたくない。
あんな目に合わさせるくらいなら殺してしまったほうがまだいい、と電撃的に直感し、手近にあった「handsaw」でもって、当時いちばん小さかった赤子=ビラヴドを殺してしまいました(そのときはまだデンバーちゃんは生まれていません)。
これ、最初のエントリーでも書きましたが、この物語のコアとなる部分のひとつです。
一番のコアは、奴隷と、子殺しと、黄泉帰りであると。
ところが、わたくしのエッセイでは、デンバーちゃん視点からの再編集というところにこだわりすぎてしまい、結局その部分の記述を盛り込みませんでした。
これはいくらなんでも、失敗だったなーと思っているところです。
たとえ、読者全員が本を読んでいるという前提であっても、ここのところを外すのはよくなかったですね。
そのために、ここの「the handsaw」が唐突になりすぎてしまいました。
はんせー。
(つづく)

- 作者: トニモリスン,Toni Morrison,吉田廸子
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 1998/12
- メディア: 文庫
- 購入: 3人 クリック: 23回
- この商品を含むブログ (12件) を見る
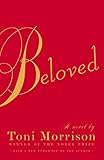
Beloved (Vintage International)
- 作者: Toni Morrison
- 出版社/メーカー: Vintage
- 発売日: 2004/06/08
- メディア: ペーパーバック
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (4件) を見る
『ビラヴド』トニ・モリスン その4
昨日のケイシー・マスグレイブス @Fuji Rock Festival、よかったですね!
最初は雨模様で心配しましたが、途中からは晴れてきて、そんな神がかりな演出のなか、代表曲の "Follow Your Arrow" へ。
ケイシーのかわいさが見事炸裂。
YouTubeのチャットでも好意的なコメントが溢れていましたね。
Kacey Musgraves - Follow Your Arrow
さて、ここからは、学校の課題で書いた英語エッセイを振り返りながら、ああだこうだ言ってみる企画の続編です。
ノーベル文学賞受賞作家であるトニ・モリスンの代表作『ビラヴド』にまつわるエッセイを取り上げています。
However, this bitter medicine worked well on Denver. Using the break of her ordinary world created by Paul D, Denver stepped out from the grounds of 124 for the first time in eight years and had fun at the carnival with Sethe and Paul D. Nonetheless, Paul D’s triumph did not last long. When they returned from the carnival, they found a drained woman lying on a stump in front of their house. It was the embodiment of the expelled ghost named Beloved. Only Denver could see such unrealistic truth. Based on her affection for Beloved, she decided to protect her returned sister at any cost. Denver later expressed her special fondness as “She played with me and always came to be with me whenever I needed her. She’s mine, Beloved. She’s mine” (Morrison, 247).
今日はさらっと1パラグラフだけ。
ポールDという外界の人間が、突然姿をあらわして、124に住む人たちの人生を大きく動かしていくわけですが、その序盤の部分ですね。
彼が居心地のいい内的空間をブチ壊してしまったので、ひきこもりのデンバーちゃんはブチ切れたわけですが、内に引きこもる理由もなくなってしまったので、8年ぶりに家の外へ出て行く決心をつけました。
黒人のためのカーニバルに出向いたのですが、これが行ってみると楽しい。悪くない。
ポールDとセサと三人でルンルンと、これからどうなっていくのかなどと淡い夢を描き始めたところで、さらなる new twist です。
ポールDに追い出されたあの霊が、形を変えて帰ってきました。
お母さんは案外すぐには分からなかったようですが、デンバーちゃんはすぐに気がつきました。
あ、あの赤ん坊の幽霊だ。
ってことは、マイ・シスターだ!

▲「マイ・シスター」のご登場。映画版より。
このあたりは、物語の序盤に起こる出来事を、終盤に明かされる裏話を差し込みつつ紹介していくという手法をとっています。
昨日カバーした部分と同じやり方です。
ストーリーテリングの豊潤な紆余曲折を無視して、時間軸でグサリと串刺しにしていく。
これが効果的だろうと思ったぼくは、後に物語記述が回想シーンを飛びこすまで、このパターンを頼りに論を進めていきました。
(つづく)

- 作者: トニモリスン,Toni Morrison,吉田廸子
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 1998/12
- メディア: 文庫
- 購入: 3人 クリック: 23回
- この商品を含むブログ (12件) を見る
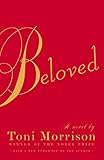
Beloved (Vintage International)
- 作者: Toni Morrison
- 出版社/メーカー: Vintage
- 発売日: 2004/06/08
- メディア: ペーパーバック
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (4件) を見る
『ビラヴド』トニ・モリスン その3
昨日今日は、YouTube で Fuji Rock Festibal の生配信を見ています。
元ミッシェルガンエレファントのチバ氏&クハラ氏だとか、元ブランキージェットシティのベンジー氏など、その姿を久しぶりに見られて興奮しました。
https://www.youtube.com/watch?v=nmcLElYe71M
この後のKACEY MUSGRAVES(アメリカのカントリーシンガー↓)の登場も楽しみにしています。
さて、ここからは、学校の課題で書いた英語エッセイを振り返りながら、ああだこうだ言ってみる企画の続編です。
ノーベル文学賞受賞作家であるトニ・モリスンの代表作『ビラヴド』にまつわるエッセイを取り上げています。
Denver is the last of Sethe’s four children. By the beginning of the story, Denver had become the only housemate of Sethe, if not counting the baby ghost, due to the back-to-back getaways of her brothers and the death of her grandmother Baby Suggs. From little before the passing of Grandma Baby, Denver had shut herself away within the grounds of their (haunted) house addressed 124 Bluestone Road and avoided contacts of outside people. She liked spending her time at a secret space hidden by bushes located far back in the backyard of 124. In the secret emerald box, she indulged herself in smelling the fragrance of collected cologne. In that moment, her soul got freed. “Denver’s imagination produced its own hunger and its own food, which she badly needed because loneliness wore her out. Wore her out.” (Morrison, 35).
However, her situation was forced to change by a visit by Paul D, one of Sethe’s slave associates at Sweet Home. While Sethe got excited and immediately started a romance with her old friend, Denver was not happy to have him at 124. It was not just because she lost attentions from her mother, who was also her only human company. In the chapter of Denver’s monologue, it was revealed that “I heard his voice downstairs, and Ma’am laughing, so I thought it was him, my daddy. […] But when I got downstairs it was Paul D and he didn’t come for me; he wanted my mother” (Morrison, 245). In addition, shortly after his arrival, Paul D somehow succeeded to expel the spiteful baby ghost from 124 in an effort of protecting Sethe and his new love. This incident did not help Denver’s disturbed feelings. Denver monologized that “Ever since I was little she was my company and she helped me wait for my daddy” (Morrison, 242).
今日は長いですが、2パラグラフ、カバーしようと思います。
まぁ、内容があまり濃くないところだからです。
Denver is the last of Sethe’s four children. By the beginning of the story, Denver had become the only housemate of Sethe, if not counting the baby ghost, due to the back-to-back getaways of her brothers and the death of her grandmother Baby Suggs. From little before the passing of Grandma Baby, Denver had shut herself away within the grounds of their (haunted) house addressed 124 Bluestone Road and avoided contacts of outside people.
まずは最初のパラグラフ(全体では3パラグラフ目)の前半部分です。
ざっくりとデンバーちゃんのキャラクターを紹介しています。
家族構成は、おばあちゃんがいて、お母さんがいて、兄弟が上に三人いて、と。
でも今は、お母さんと赤ん坊の霊(赤子のときに死んだお姉さんの幽霊)とひっそりと生活しているというところです。
最初のうちは、主人公一家が幽霊屋敷に住んでいるというのが物語のキャッチーなところなのですが、それが実はやんごとなき事情によりお母さん(セサ)に殺されてしまった子供の幽霊で、のちにビラヴドと名乗る少女として「よみがえり」してくるという具合いに大展開していきます。
そのあたりをある程度カバーしつつ、
- Grandma Baby:おばあさんの名前が "Baby"
- 124:住所からとったおウチの呼び名
という混乱しかねない名詞に関してのフォローも入れています。
She liked spending her time at a secret space hidden by bushes located far back in the backyard of 124. In the secret emerald box, she indulged herself in smelling the fragrance of collected cologne. In that moment, her soul got freed. “Denver’s imagination produced its own hunger and its own food, which she badly needed because loneliness wore her out. Wore her out.” (Morrison, 35).
同パラグラフの後半部分は、デンバーちゃんの印象的な秘密基地の話です。
エメラルドグリーンの秘密基地のイメージが好きだったので、引用付きで盛り込んでいます。

▲エメラルドグリーンの秘密基地のイメージ
However, her situation was forced to change by a visit by Paul D, one of Sethe’s slave associates at Sweet Home. While Sethe got excited and immediately started a romance with her old friend, Denver was not happy to have him at 124.
さて次の段落は、デンバーちゃんとお母さんのお友達であるポールDさんとの関係について。
引きこもり一家のところに、お母さんのプランテーション時代のお友達のポールDさんがやってきたことによって、物語が展開していきます。
だけどデンバーちゃんは出会ったそのときから、ポールおじさんのことが嫌いです。
なぜだろうか。
It was not just because she lost attentions from her mother, who was also her only human company.
まずひとつめは、たった一人の身寄りであるお母さんの存在が遠のいてしまうから。
社会とのつながりの乏しい子供にとっては、それは相当な脅威に感じられることでしょう。
でも、それだけではありません。
In the chapter of Denver’s monologue, it was revealed that “I heard his voice downstairs, and Ma’am laughing, so I thought it was him, my daddy. […] But when I got downstairs it was Paul D and he didn’t come for me; he wanted my mother” (Morrison, 245).
これは本当は二百ページも先になってようやっと明かされる話なのですが、
彼女がずーーっとその帰りを待っていた、お父さんがついに自分を助けに来たのかと思ったのに、そうではなく、知らないおっさんがお母さんを奪いにきたということだったから。超ガッカリ。
In addition, shortly after his arrival, Paul D somehow succeeded to expel the spiteful baby ghost from 124 in an effort of protecting Sethe and his new love. This incident did not help Denver’s disturbed feelings. Denver monologized that “Ever since I was little she was my company and she helped me wait for my daddy” (Morrison, 242).
そしてそれどころか、唯一の仲間であった赤ん坊幽霊まで追い出されてしまった。
助けてくれないだけではなく、彼の要らぬ活躍によって、デンバーちゃんはひとりぼっちの谷底に蹴落とされてしまったわけです。
だから少女はつっけんどんだったのです。
これだけの理由があったのです。
(つづく)

- 作者: トニモリスン,Toni Morrison,吉田廸子
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 1998/12
- メディア: 文庫
- 購入: 3人 クリック: 23回
- この商品を含むブログ (12件) を見る
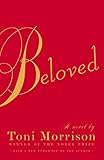
Beloved (Vintage International)
- 作者: Toni Morrison
- 出版社/メーカー: Vintage
- 発売日: 2004/06/08
- メディア: ペーパーバック
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (4件) を見る
『ビラヴド』トニ・モリスン その2
学校の課題で書いた英語エッセイを振り返りながら、ああだこうだ言ってみる企画の続編です。
ノーベル文学賞受賞作家であるトニ・モリスンの代表作『ビラヴド』にまつわるエッセイを取り上げています。
Beloved is partially based on a true tragic incident of a fugitive slave mother happened in Cincinnati, Ohio in 1856, however; the ghost character assures the story being detached from reality. It takes place between a slave state of Kentucky and a free state of Ohio, and before and after the Civil War. Episodes in Kentucky are mostly consisted of memories of Sethe and her slave associates at a slave-owning plantation Sweet Home in the pre-Civil War period, including those of escaping from Sweet Home in 1855. In the free state Ohio, there are two main time settings, the past in 1855 and the present in 1873. In the “past,” Sethe gets away from the slave state and kills her child while in the “present,” she receives a return visit of the spirit of her dead baby. Beloved is composed of such a complicated mixture of location, generation, and narration, which comes and goes over the border of the world of slavery and post-slavery over and over again. From this structural point of view, the role of Denver seem to become highly important in the story. One of the character’s attributes of being born after Sethe left the plantation and therefore not directly belonging to the world of slavery stands out.
さて、ここは手前味噌ながら、わたくしの持てる分析力・解析力をフルに発揮しているところです。
なかなかおもしろい見方を立ち上げられたのではないかと自負しています。
引用の後半部分にも書いていますが、この物語ではナレーションが予告もなしにあっちこっちに飛び回ります。
それが妙味でもあるのですが、正直、厄介でもあります。
簡単に一読しただけでは、物語世界をしっかり捕まえることはできないでしょう。普通は。
そんな自由気ままな水先案内に惑わされずに、時間軸と空間軸を縦横に引いて、物語世界を俯瞰してみせたのが前半部分となっています↓↓↓
It takes place between a slave state of Kentucky and a free state of Ohio, and before and after the Civil War. Episodes in Kentucky are mostly consisted of memories of Sethe and her slave associates at a slave-owning plantation Sweet Home in the pre-Civil War period, including those of escaping from Sweet Home in 1855. In the free state Ohio, there are two main time settings, the past in 1855 and the present in 1873. In the “past,” Sethe gets away from the slave state and kills her child while in the “present,” she receives a return visit of the spirit of her dead baby.
時間と空間、それぞれの分水嶺には、南北戦争(もしくは the 13th Amendment)と州境であるオハイオ川を置いています。
それらは奴隷世界と奴隷解放後の世界を隔てる象徴物として機能しています。
その線より向こうには奴隷世界が、手前には奴隷解放後の世界が広がっているというわけです。
向こう側の世界には、プランテーションの思い出や、逃亡・出産の記憶、そして子殺しの記憶が属していて、
こちら側には、ビラヴドの訪問やそれ以降の新しい家族計画が属しています。

From this structural point of view, the role of Denver seem to become highly important in the story. One of the character’s attributes of being born after Sethe left the plantation and therefore not directly belonging to the world of slavery stands out.
そして、ナレーションがあちこち飛び回るという泣き言をはさんで(笑)
デンバーちゃんというキャラクターの構造的特徴をズバリ言い当てています(と思っています)。
それは、デンバーちゃんが生まれたのが、奴隷制廃止前とはいえ、プランテーション内ではなく自由が保証されるオハイオ州であり、彼女の人生は直接的には、奴隷制とは関わりがないというものです。
この属性が、奴隷制をテーマにしているこの物語を理解するための鍵になる、という読みを展開しています。
(つづく)
『ビラヴド』トニ・モリスン その1
学校の課題で書いた英語エッセイを振り返りながら、ああだこうだ言ってみる企画です。
まずはノーベル文学賞受賞作家であるトニ・モリスンの代表作『ビラヴド』にまつわるエッセイを取り上げてみます。
Denver Not Belonging to the Slavery
Toni Morrison’s Beloved is centered on experiences of a former fugitive slave Sethe. Two of its key episodes are her experiences of killing her own child in an attempt of family suicide (as a last resort to protect her children from the chains of slavery), and having a “return visit” of a 19-to-20-year-old woman named Beloved, who is believed to be the embodiment of the grown-up spirit of the murdered baby. That said, in order to understand the meaning of Beloved, I believe the third character of Denver should be focused on rather than Sethe or Beloved. Therefore, I will firstly confirm the significance of Denver’s role by examining the structure of the story, and then analyze the meaning underneath the storyline from the viewpoint centered on the character of Denver.
最初の太字がタイトルで、残りはそれに続くファーストパラグラフ。
このタイトル("Denver Not Belonging to the Slavery")は弱い。弱いなー。自分でもわかるくらい弱い。
本当は考え直したかったのだけど、締め切りまでにいいのが思いつかなかったのでした。
今であれば "From Outside of the Slave Plantation" とかにするでしょうか。
ほぼ同じ内容を盛り込みつつ、引き締めてみました。
デンバーちゃんを主題に据えているということを、直接的に言ってしまいたいのですが、それをグッとこらえてガマンしたというのがポイントです。
また、第三者視点だったのをデンバー視点にしたことで、臨場感が少しは出せているし、彼女の存在を匂わすこともできているのじゃないかと思います。
Toni Morrison’s Beloved is centered on experiences of a former fugitive slave Sethe. Two of its key episodes are her experiences of killing her own child in an attempt of family suicide (as a last resort to protect her children from the chains of slavery), and having a “return visit” of a 19-to-20-year-old woman named Beloved, who is believed to be the embodiment of the grown-up spirit of the murdered baby.
ファーストパラグラフ、冒頭からなかなか大胆に攻め入っているでしょう。
とはいえ、誰が読んでもそうだよね、という物語のコアイベントの取り出しであり、そこに独自性などは見られません。
どちらかと言えばここでやっているのは、他の箇所を思い切って捨てるということです。
いちばん短い説明文を書く場合に記載されるべきもの、というつもりで考えてみました。
それが、「逃亡奴隷」「子殺し」「幽霊になっての帰還」の3点でした。
2センテンス目がひどく長いわけですが、これをスッと3つのセンテンスに分けるとかができないのが、今の自分の英語力の限界部分となっとります。
だいたい文章が長くなりすぎるのが、わたくしめのクセなのです。
日本語でも似たようなもんでしょうが、英語だとさらにそのあたりのハンドリングがむつかしい。
丸カッコなどを入れてごまかしていますが、それが吉と出ているか凶と出ているのかは、自分では判断つきません。
まぁ、嫌われる可能性が結構ある文章になっているというのはわかります(泣)
That said, in order to understand the meaning of Beloved, I believe the third character of Denver should be focused on rather than Sethe or Beloved. Therefore, I will firstly confirm the significance of Denver’s role by examining the structure of the story, and then analyze the meaning underneath the storyline from the viewpoint centered on the character of Denver.
後半部分、これはタイトル以上に弱いでしょう(号泣)
いわゆる thesis statement の部分なのですが、それがどういうものだったか忘れた状態で、こんな風にするんだっけか? という当てずっぽうでやったら見事に外れてしまったという代物です。
それをセンセーに「ご査収ください」とやってしまった…。
最初のセンテンスの「I believe」なんてのはここでは要りませんね。
ふたつめのセンテンスの運び方もふさわしくない。
「このエッセイではこういうことをしてみるつもりです」なんていうのは、求められていないのです。
冒頭で一番言いたいことを書け! というアメリカスタイルを金科玉条とは思っていないのですが、そういうこともできるようにしておくのは、これからアメリカやらグローバルな世界やらで生きていくには、大切なスキルということになってくるでしょう。
ということで、ウダウダ言うのをいったん止めて、やってみます。
わたくしの元の文章では、
「しかし、この物語を深く理解するためには、セサやビラヴドではなくて、三人目のキャラクターであるデンバーちゃんに注目する必要がある。であるから、まず最初に物語の構造を精査することにより、デンバーちゃんの役柄の重要性を再確認し、そして、そのキャラクターの視点でもって、物語の奥にある隠れた意味を探りたい」
というようなことを書いています。
これを、アメリカ的に言い切るようにしてみます。
この「奥にある隠れた意味」というのを言ってしまうということでしょうね。
「しかし、この物語を深く理解するためには、セサやビラヴドではなくて、三人目のキャラクターであるデンバーちゃんに注目する必要がある(ここまで同じ)。セサやビラヴドが経験した困難に加えて、奴隷システムの外で生まれ育ったデンバーちゃんの成長物語を見ることではじめて、奴隷システムが people of color に与えた今なお消えない烙印(スティグマ)の全体像が浮かび上がってくる」
とかなんとか。

▲ビラヴド映画版より。左からデンバーちゃん、セサ、ビラヴド。
これでどうでしょう。
エッセイ導入としては、少しはマシになったでしょうかね。
このエッセイ、長短ありますが、あと10パラグラフあります。
まだ先は長い。
ひとまずこの企画を完遂するのが目標です。
【橋爪大三郎×大澤真幸】理不尽や不可解を担える存在
目次*1
アメリカに住んでいるので、やっぱりアメリカのことをよく知りたい、自分なりに理解したい、そうでなければ現状が浮かばれないじゃないか。そういう思いで、内田センセイのアメリカ論に続き、手に取った本である。アメリカの紀伊国屋書店の新書コーナーには、こういう類の本が並べられている。どうも一定の共感を得られる、よくある思考のようである。
講談社現代新書は現在、同型色違い装丁を採用しているが、この本にはキラキラの金色が与えられている。そんな味気のないデザインの是非は置いておくと、推し、が感じられる表紙である。帯には高橋源一郎さんからこんな言葉が寄せられていた。
「読んだだけで、キリスト教が完全に理解できたような気がする、他に例のない恐ろしい本。とりあえず、ぼくのゼミの必読書に決定しました」
キリスト教を完全に理解できたような気になるほどの本から、無謀にもハイライトをつくってみた。高橋センセイ、どうですか? このくらいじゃゼミの単位は貰えないのでしょうか。

橋爪 一神教は、たった一人しかいない神(God)を基準(ものさし)にして、その神の視点から、この世界を視るということなんです。たった一人しかいない神を、人間の視点で見上げるだけじゃダメ。それだと一神教の半分にしかならない。残りの半分は、神から視たらどう視えるかを考えて、それを自分の視点にすることなんです。(p.55)
この世界には、神に好かれる人もいるし、好かれない人もいる。人間の理解を超えた理不尽なこともおこる。しかし、一神教の神はそれ自体が基準なので、ほかの理由なしに、いついかなるときも正しいのである。神は世界でおきる一切のことの責任者であり、究極の原因である。人間が納得しないといって、わざわざ説明してやる義理はないのである。
人と対話可能というのも、この人格的Godの特徴だ。ただしそれは、人間がコミュニケーションの不可能性を受け入れるというコミュニケーションである。「祈り」と呼ぶ。人間を救うのは神であり、人間は自分で自分を救えない。人生における艱難辛苦は、神に与えられた試練として受け入れ、乗り越えていくことが期待されている。が、その通りに行動したとしても、救ってもらえるとは限らない。それがGod視点だ。
大澤 イエスは、律法を廃棄して、それを愛に置き換えた。ただ、律法を単純に否定し、排除したというより、むしろ、愛こそが律法の成就だということになっています。(中略)その愛のことを、「隣人愛」という。「隣人」と聞くと、身近で親しい人のことだと思うかもしれませんが、そうではない。罪深い人ととかダメな人とかよそ者とか嫌な奴、そういう者こそが、「隣人」の典型として念頭におかれていて、彼らをこそ愛さなくてはならない。(p.195)
ジョーゼフ・キャンベルがイエス・キリストの主要な教えとして挙げていたのが「隣人愛」だった。隣人愛のいちばん大事な点は「裁くな」ということ。人が人を裁くな。人を裁くのは神だからである。
不完全な人間は、神に与えられた「律法」を完全には守ることができない。それどころか眼前の律法の正しさに固執しすぎて、かえって神の意向に沿わぬ裁きを下したりもする。そこでイエスが現れ、律法を愛に置き換えた。愛も律法も、神と人間の関係を正そうとする努力であるが、愛には基準がないので、これで十分に愛したなどと人が慢心する心配が少ないのだ。
橋爪 キリスト教の優位については、いろいろに言えると思うのです。宗教改革も大事だし、新大陸の発見も大事だし、科学技術の発展や産業革命も大事だし、資本主義も大事だ。
でも、最も根本的なところで、いちばん大事な点を取り出すとすれば、それはキリスト教徒が、自由に法律をつくれる点だと思う。(p.274)
なぜ、ユダヤ教やイスラム教といった他の一神教ではなく、キリスト教が世界の主導権を握ったのか。それはキリスト教徒が(その国家が)、自由に新しい法律をつくれたからだ。
たとえば「銀行をつくって、企業にローンを組ませる」というように、社会が近代化へ向けた具体的なステップを踏み出そうとしたときに、厳格なユダヤ教やイスラム教の場合、それが宗教法で「してもよい」正しいことに制定されているかしっかり確認・議論・再確認をしなければならないのだが、キリスト教の場合は、聖書で「してはいけない」と禁止されていないことは基本的にやっていいので、圧倒的にスムーズだったのだ。
そうなった要因の真ん中あたりに、「教会が法律をつくらない」ということがある。キリスト教の教会はもともと、ローマ帝国の任意団体でしかなく、そのような力を持っていなかった。それゆえ、ローマ帝国の法律(世俗法)に従いましょうということになり、立法権を占有するということがなかった。それが近代化には都合がよかったのだ。
* * *
STAP細胞や号泣議員、スアレスの噛み付き行為ーー我々の社会を鑑みてみると、宗教の影響力が弱くなったせいか、人が人の罪を野方図に裁きすぎているという感じがする。犯した罪に対して世俗法によって罰が与えられることは、そりゃ当然理解するが、されども、彼らをこそ愛そうという声があがらないのは虚しいことだと思うのだ。
アメリカはどうだろうか。同じようなもんだっけ。
* * *
追記:たまたまブログでSTAP細胞に言及したタイミングで、理研の笹井芳樹氏が自死した。会見の姿に研究者としての矜持を見て、美しく尊いものを感じていたので非常に残念に思う。俺たちが生きているのは、美しい花が咲いていられない泥の中なのか。宗教はなにをやっているんだ。まったく。合掌。
*1:
まえがき
第1部 一神教を理解するーー起源としてのユダヤ教
1 ユダヤ教とキリスト教はどこが違うか
2 一神教のGodと多神教の神様
3 ユダヤ教はいかにして成立したか
4 ユダヤ民族の受難
5 なぜ、安全を保障してくれない神を信じ続けるのか
6 律法の果たす役割
7 原罪とは何か
8 神に選ばれるということ
9 全知全能の神がつくった世界に、なぜ悪があるのか
10 ヨブの運命ーー信仰とは何か
11 なぜ偶像を崇拝してはいけないのか
12 神の姿かたちは人間に似ているか
13 権力との独特の距離感
14 預言者とは何者か
15 軌跡と科学は矛盾しない
16 意識レベルの信仰と態度レベルの信仰
第2部 イエス・キリストとは何か
1 「ふしぎ」の核心
2 なぜ福音書が複数あるのか
3 奇蹟の真相
4 イエスは神なのか、人なのか
5 「人の子」の意味
6 イエスは何の罪で処刑されたか
7 「神の子」というアイデアはどこから来たか
8 イエスの活動はユダヤ教の革新だった
9 キリスト教の終末論
10 歴史に介入する神
11 愛と律法の関係
12 贖罪の論理
13 イエスは自分が復活することを知っていたか
14 ユダの裏切り
15 不可解なたとえ話1 不正な管理人
16 不可解なたとえ話2 ブドウ園の労働者・放蕩息子・九十九匹と一匹
17 不可解なたとえ話3 マリアとマルタ・カインとアベル
18 キリスト教をつくった男・パウロ
19 初期の教会
第3部 いかに「西洋」をつくったか
1 聖霊とは何か
2 教義は公会議で決まる
3 ローマ・カトリックと東方正教
4 世俗の権力と宗教的権威の二元化
5 聖なる言語と布教の関係
6 イスラム教のほうがリードしていた
7 ギリシア哲学とキリスト教神学の融合
8 なぜ神の存在を証明しようとしたか
9 宗教改革ーープロテスタントの登場
10 予定説と資本主義の奇妙なつながり
11 利子の解禁
12 自然科学の誕生
13 世俗的な価値の起源
14 芸術への影響
15 近代哲学者カントに漂うキリスト教の匂い
16 無神論者は本当に無神論者か?
17 キリスト教文明のゆくえ
あとがき
文献案内






